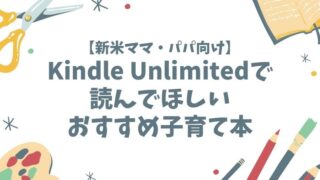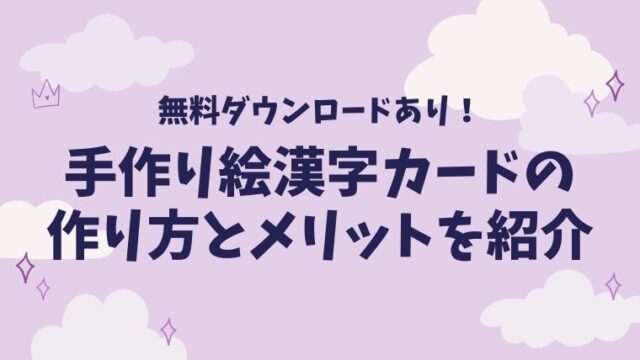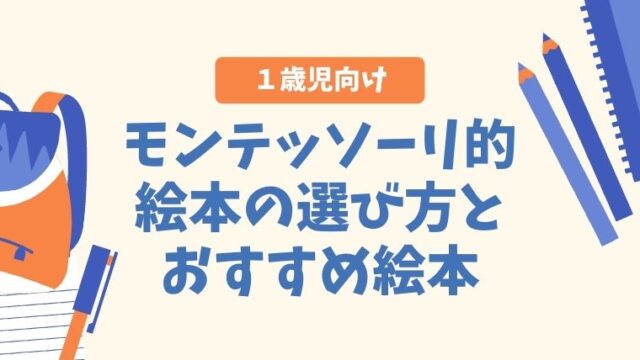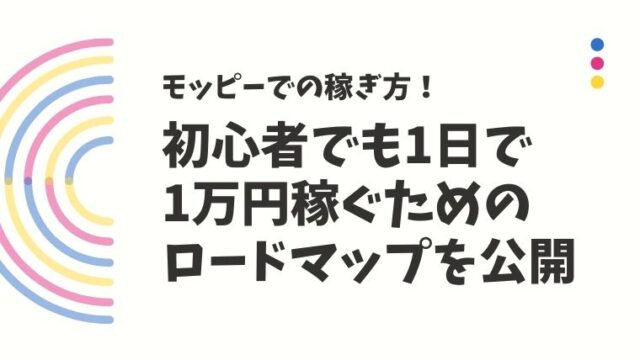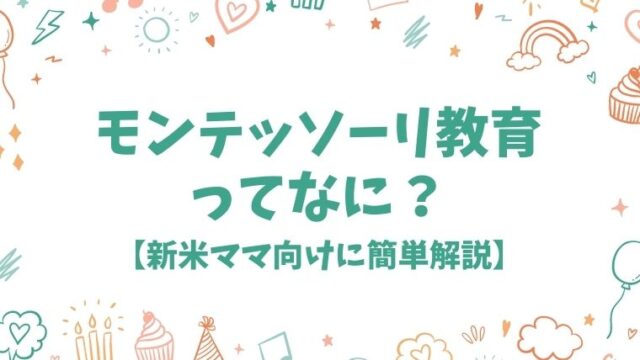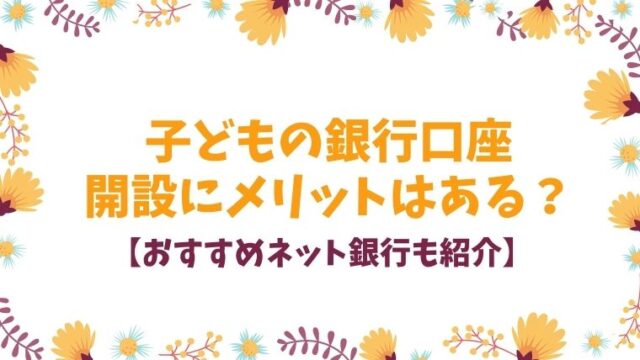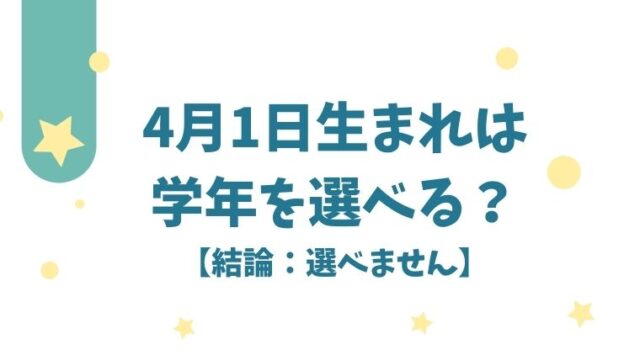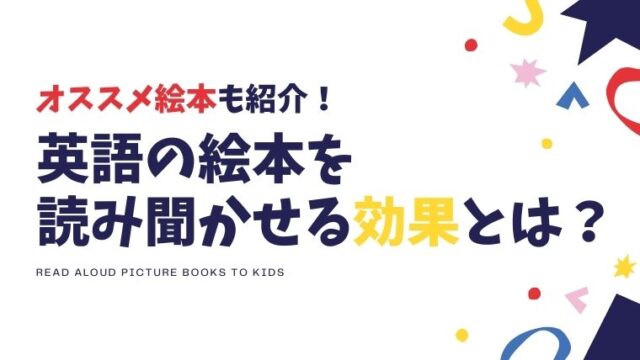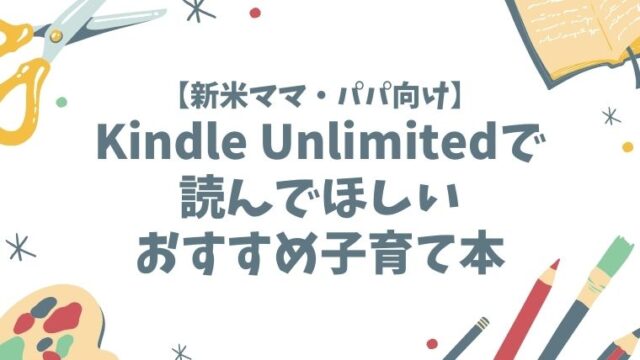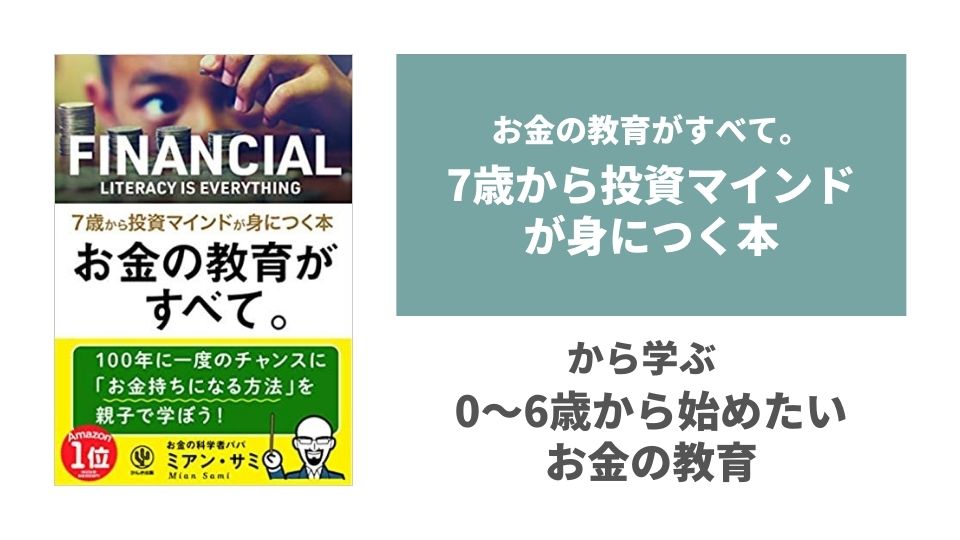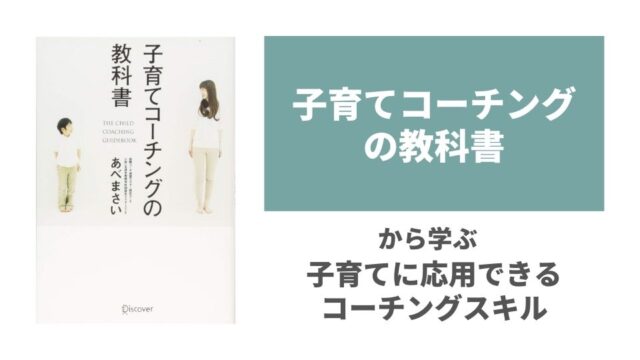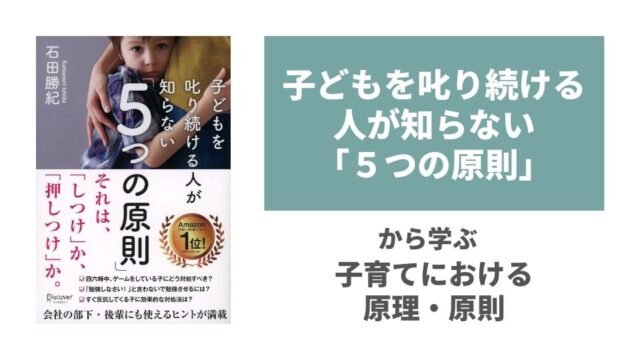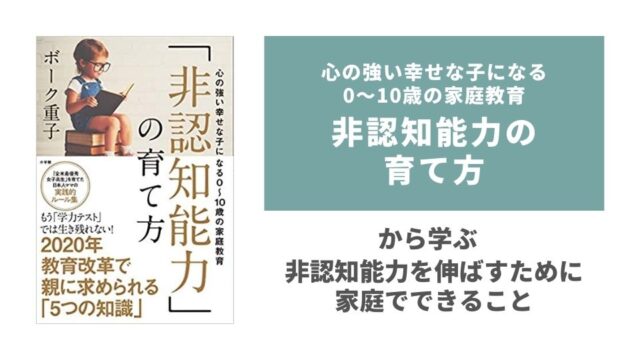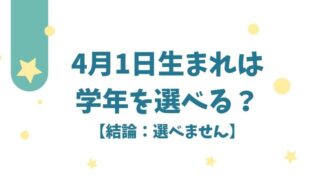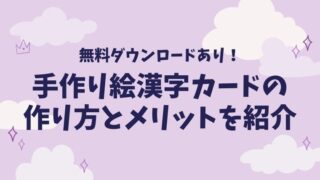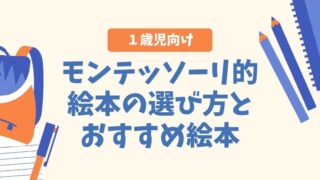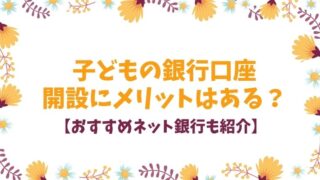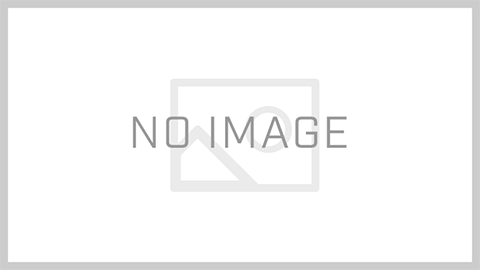・お金の教育が全てである理由
・お金の教育を始める前に親が持っておきたいマインドセット
・子どもが0〜6歳のうちからやっておきたいお金の教育
この記事では
- お金の教育がすべてってどういうこと?
- お金の教育って何をやったらいいの?
- 子どもが小さいころからお金の何にについて教えた方がいいの?
といった疑問に「お金の教育がすべて。 7歳から投資マインドが身につく本|ミアン・サミ」を参考文献にしてお答えしていきます。
親であるわたしたちのほとんどが「お金」についてキチンと学んだことがないため、このままでは子どもに教えることもできません。
子どもに正しい知識を伝えていくためにも、お金の教育について概要をサクッと理解しておきましょう!
お金の教育が全てである3つの理由
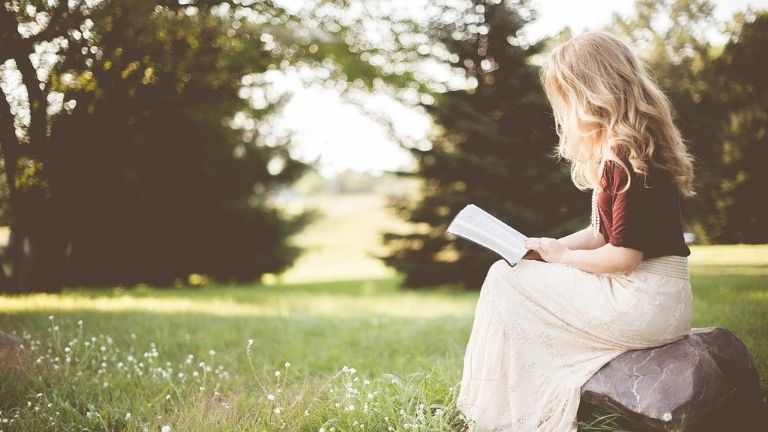
「お金の教育が全て」である理由は、主に以下の3つです。
- 世の中のあらゆることが理解できるようになる
- 幸せの根源である「安心」と「自由」が両立できるようになる
- 子どもの能力が無限に広がる
世の中のあらゆることが理解できるようになる
お金の教育によって「世の中のあらゆることが理解できる」ようになります。
なぜなら、お金とは「誰かの問題を解決することで生み出されるもの」だからです。世の中の誰かを「ハッピー」にした対価が「お金」です。
たとえば、以下のように
■ 悩み
・子育てで忙しくて家の掃除まで手が回らない…
■ 解決策
・家事代行とママのマッチングサービス
■ 結果
・家がキレイになりママが「ハッピー」になる
ママが「ハッピー」になった対価として、家事代行の方へ「お金」が支払われているんですね。
このように「これはどんな人をハッピーにしているのか?」と考えることで、世の中の仕組みを理解することができるようになります。
よって、お金の教育により「世の中のあらゆることが理解できる」ようになれるのです。
幸せの根源である「安心」と「自由」が両立できるようになる
お金の教育によって、幸せの根源である「安心」と「自由」が両立できるようになります。
著者のミアン・サミ氏に曰く、安心と自由の両方を手に入れる生き方をする人を「リッチマインド」と呼びます。
リッチマインドの逆は「プアマインド」です。
■ リッチマインド
ビジネスオーナーや投資家のように、ビジネスやお金を働かせて収入を得ている
■ プアマインド
会社員や自営業者のように、自分の時間を切り売りして収入を得ている
お金を働かせるためには「投資」をすることが必須であり、そのためにはお金の教育が欠かせません。
以上の理由から、「安心」と「自由」を両立したリッチマインドになるためにもお金の教育は大切になってきます。
子どもの能力が無限に広がる
お金の教育により、子どもの能力を無限に広げることができます。
なぜならお金を勉強することにより
- 数字に強くなる
- 英語が身に付く
- 自己肯定感が高まる
- グローバル思考になる
などの能力アップが期待されるからです。
■ 数字
→ お金を計算することにより数字に強くなる
■ 英語
→ 投資などを学ぶために海外のウェブサイトなどで情報収集することに英語に強くなる
■ 自己肯定感
→ テストや偏差値などから開放されることで自己肯定感が高まる
■ グローバル思考
→ 世界を俯瞰して見れるようになるためグローバル思考が身に付く
なるほどと思ったのは「自己肯定感」についてです。
これまで「お金を稼ぐにはいい大学に行って、大企業に就職するしかない!」といった「一辺倒な思考」から脱却することにより、別な角度からも自己肯定感を高めることが可能なんですね。
お金の教育により子どもの能力も無限に伸ばすことができます。
お金の教育を始める前の親のマインドセット

お金の教育を始める前に、まずは親のマインドを変える必要があります。
- お金に対する偏見を外してみる
- ポジティブな言葉を使うようにする
- 日常生活の中で「お金」について話し合うようにする
お金に対する偏見を外してみる
自らの「お金に対する偏見」を外すことが大切です。
なぜなら親のお金に対する偏見は、子どもにも伝染するからです。
「お金のことを話すのは下品だ!」
「お金は汗水垂らさないと稼げないものだ」
「お金を稼ぐには自分の時間を切り売りするしかない」
などの「偏見」があれば、そこを変えるところから始めます。
ポジティブな言葉を使うようにする
普段から「ポジティブな言葉」を使うように心掛けます。
ネガティブな言葉を使っていると、本人の潜在意識にどんどんとネガティブな意識が刷り込まれてしまうからです。
たとえば
「投資するお金なんてないよ!」
↓
「どうやって投資するお金を作り出そうか?」
「お金の勉強をする時間がない!」
↓
「定期的にお金の勉強をするにはどうしたらいいかな?」
上記のように、ネガティブな言葉を「ポジティブな言葉」に言い換えます。そうすることで頭は解決策を探し始めるんですね。
子どもに教育を始める前に、まずは親がポジティブな言葉を使うことが大切です。
日常生活の中で「お金」について話し合うようにする
日常生活の中で「お金」について話し合うように心掛けます。
「お金の教育をしよう!」と意気込むのもいいですが、日常生活のちょっとした瞬間にもお金の教育は実践できます。
たとえば
- スーパーで買い物をするとき
- 電車やバスに乗ったとき
- クレジットカードやプリペイドカードを使うとき
などです。
「商品の価格はどうやって決まるのだろう?」
「電車やバスに乗るときは、モノは手に入らないけどなぜお金がかかる?」
「クレジットカードを使うとなんで買い物ができるの?」
などと、実はお金の教育ができる瞬間は生活の中にたくさんあります。
ぜひ日常生活の中のちょっとした出来事を活かしてお金の教育を実践していきましょう。
0〜6歳のうちからやっておきたいお金の教育
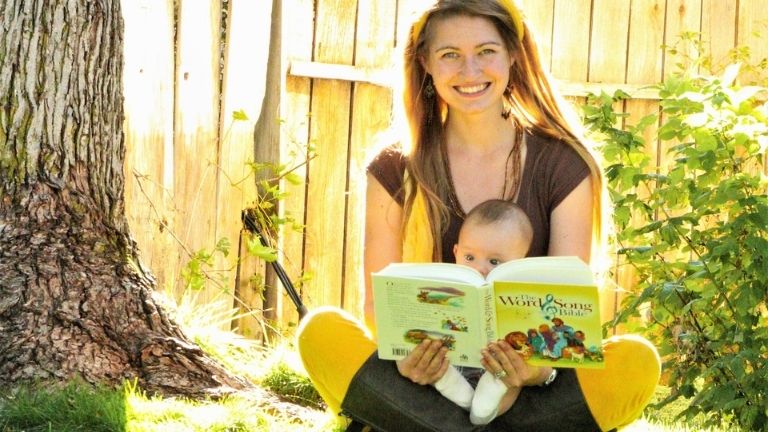
0〜6歳(未就学児)から意識したいお金の教育は、以下の3点です。
- お金の本質について話す
- どんなところでお金が使われているか体験する
- お金について知る機会を増やす
お金の本質について話す
0〜6歳のうちからでも「お金の本質」について話しましょう。
お金とは「人の悩みや問題を解決して、人をハッピーにしたら作れるもの」と著者のミアン・サミ氏は言います。
「お金は、誰かをハッピーにしたら作れるもの」
「どうやったら人をハッピーにできるのか」
「人の悩みを知るにはどうしたらいいのか」
とったことを含め、子どもとコミュニケーションを取るようにします。
そうすることで「お金とは何か、どうすればたくさんもらうことができるか」という本質を理解させることができます。
どんなところでお金が使われているか体験する
お金が日常生活のどんなところで使われているか体験するところから始めるようにします。
0〜6歳のうちはまだお金がどんなところで使われているかをそもそも知らないからです。
- スーパーやコンビニなどのお店
- 電車や新幹線などの乗り物
- 電気や水道などの公共料金
お金を使っているからこそ利用できている「モノやサービス」を体験させてあげ、そのたびにお金が使われていることを説明してあげましょう。
お金について知る機会を増やす
子どもがお金について知る機会を増やすことも大切です。
お金の教育は堅苦しいものではなく、日常生活のちょっとした瞬間に「お金について知る機会」があれば実践できるものです。
たとえば
- スーパーの買い物の金額を計算させてみる
- 小銭に触れさせていくらあるか数える
- おもちゃはいくらで買えるか考えさせる
などの、ちょっとした瞬間。
そのためには、当然ですが親子のコミュニケーションが欠かせません。
お金の教育のためにガッツリ時間を割く、というより日常生活のちょっとした瞬間を使ってお金を知る機会を増やしましょう。
まとめ
この記事では
- お金の教育が全てである3つの理由
- お金の教育を始める前の親のマインドセット
- 0〜6歳のうちからやっておきたいお金の教育
についてお伝えしてきました。
今回は0〜6歳の子ども向けの教育についてのみ書いてきましたが、本書の「お金の教育がすべて。 7歳から投資マインドが身につく本|ミアン・サミ」では
- 7〜15歳の小中学生にお金をどう教えるか
- 16〜18歳の高校生にお金をどう教えるか
についても解説されています。
子どもが大きくなってからでもお金の教育でできることはあります。気になる方はぜひ本書をお読みください!
普段の生活の中にこそお金の教育を溶け込ませていこうと思いました!