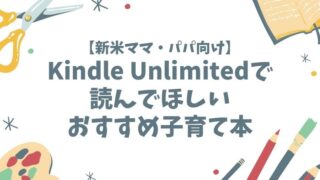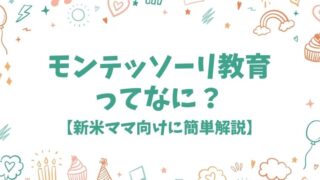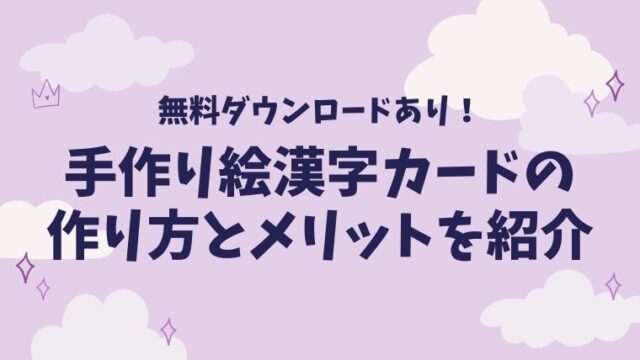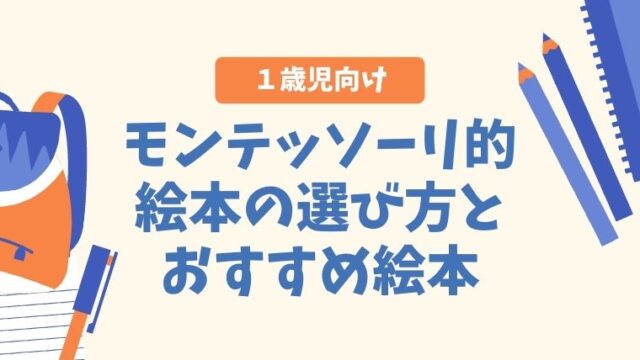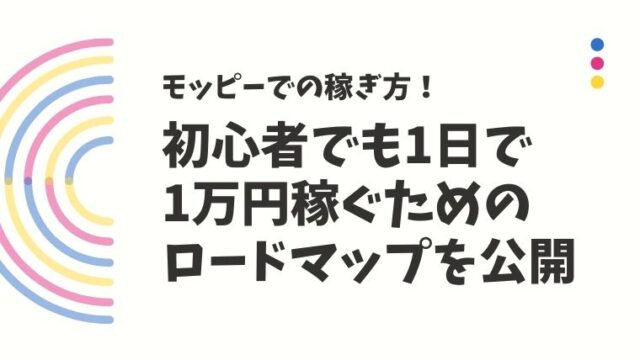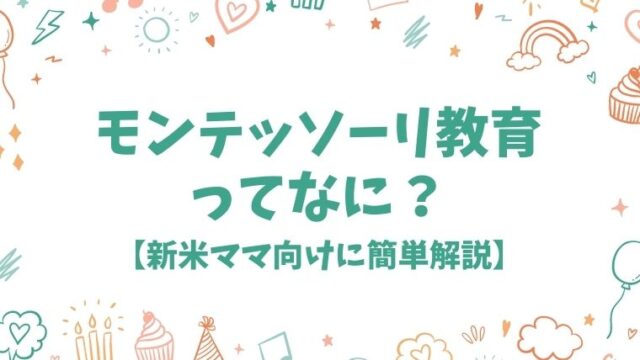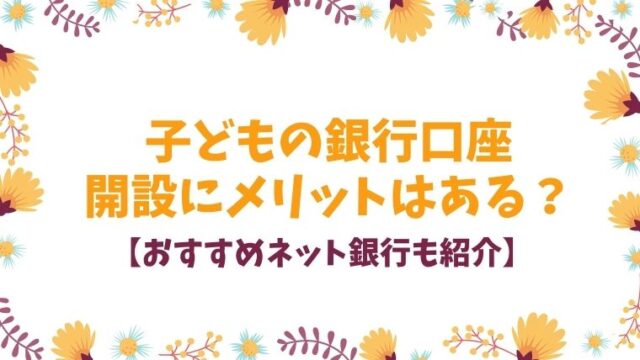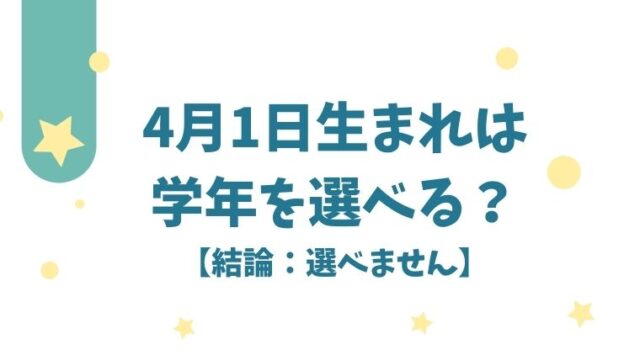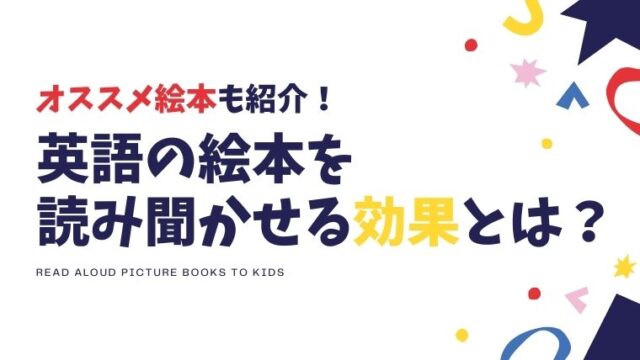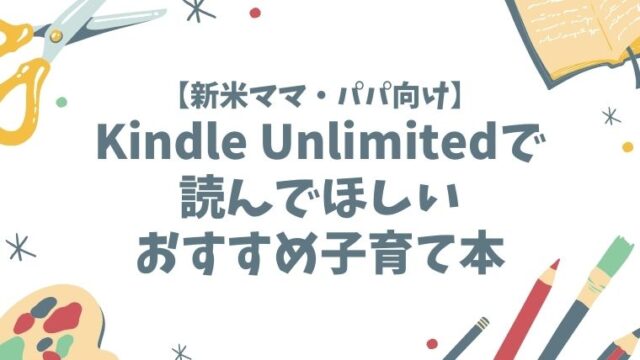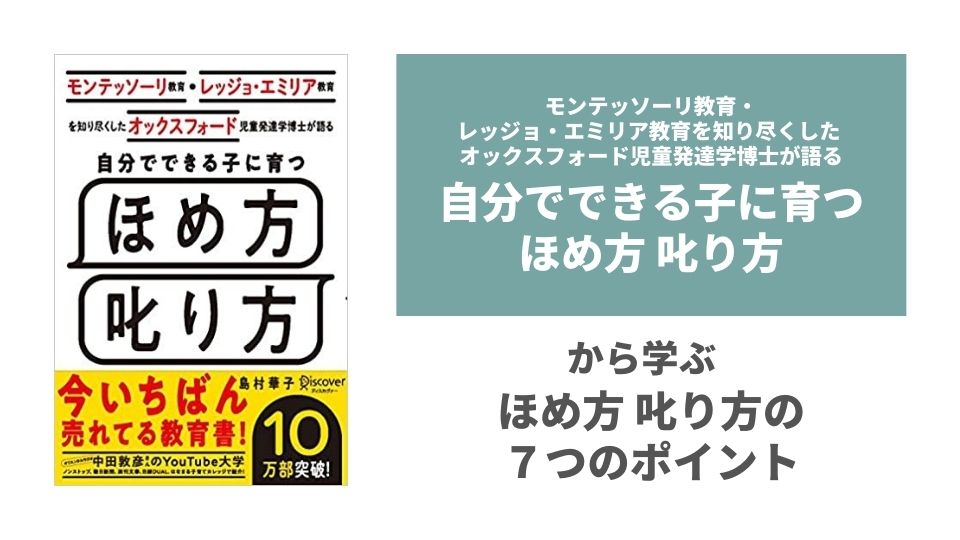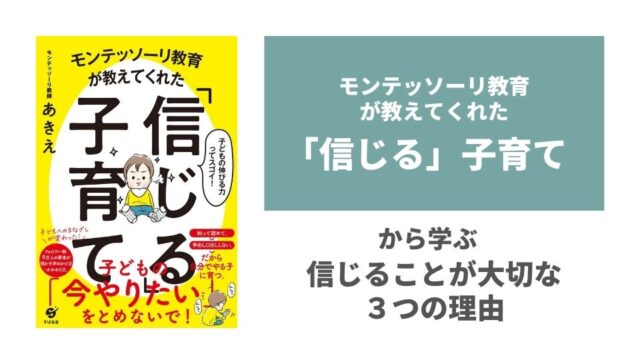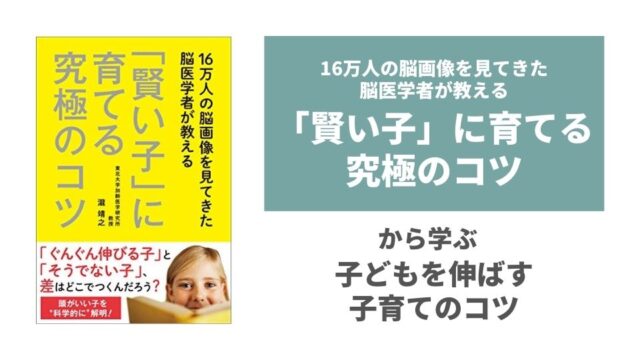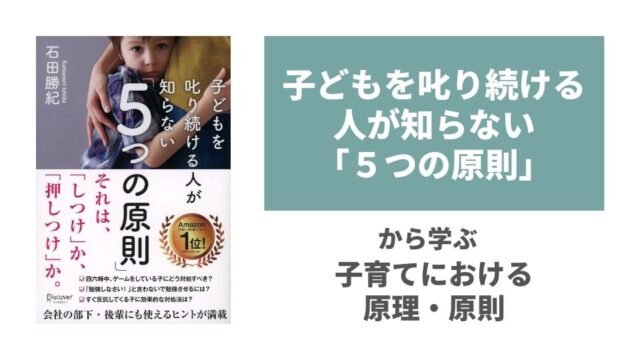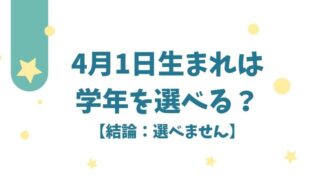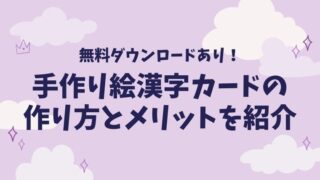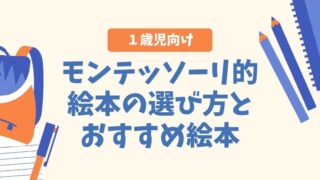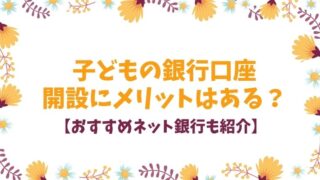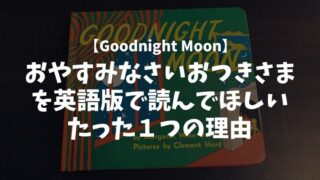■ この記事の対象者
・0〜12歳の子どもがいる方
・子どもの正しいほめ方、叱り方が知りたい方
・子どもの能力を伸ばして上げたい方
この記事では
- 子どもに対する正しいほめ方・叱り方ってどうやるの?
- 子どもが伸びるほめ方・叱り方を教えてほしい…
- 叱り続けても子どもが分かってくれなくてツライ…
といった疑問・お悩みに、「自分でできる子に育つ ほめ方 叱り方|島村華子」を参考文献にしてお答えしていきます。
また、本書はKindle Unlimitedでも読むことができます。
\ 無料で30日間お試し可能!/
自分でできる子に育つ「ほめ方」

3種類のほめ方を把握する
「ほめ方」には3種類あります。
- おざなりほめ
- 人中心ほめ
- プロセスほめ
それぞれの特徴は以下の通りです。
■ おざなりほめ
「すごい!」「うまくできなね!」など、具体性のない表面的なほめ方。
■ 人中心ほめ
「優しいね!」「かわいいね!」など、性格・能力・外見の特徴をほめる。
■ プロセスほめ
「かんばって勉強したね」「何度も繰り返し練習したね」など、努力・過程・試行錯誤した手順をほめる。
参考:自分でできる子に育つ ほめ方 叱り方|島村華子
結論を述べると、子どもをほめるときは「プロセスほめ」をするようにします。「おざなりほめ」「人中心ほめ」ではいけません。
プロセスをほめるようにする
子どもをほめるときは、基本的に「プロセスほめ」をするようにします。
なぜなら「おざなりほめ」「人中心ほめ」にはデメリットが大きいからです。
おざなりほめ・人中心ほめをすると
- ほめられ依存症になる
- 興味を失う
- チャレンジ精神が低下する
などのデメリットがあります。理由は以下をご参考ください。
■ ほめられ依存症になる
→ ほめられないと自信が持てなくなる
→ 外部からの承認でしか自分の価値を見いだせなくなる
■ 興味を失う
→ 好きだから、ではなく褒められるためだけに行動するようになる
→ ほめられなくなった途端「もういいや」と興味を失う
■ チャレンジ精神が低下する
→ 周囲からの評価が下がることを恐れ、失敗を避けるためにチャレンジしなくなる
よって子どもをほめるときは「プロセスほめ」をするようにします。
ほめ方の3つのポイント
「ほめ方」のポイントは、以下の3つです。
- 成果よりもプロセスをほめる
- もっと具体的にほめる
- もっと質問する
1. 成果よりもプロセスをほめる
プロセスとは
- 努力したこと
- 挑戦した姿勢
- やり方を工夫したこと
などのことです。
テストでいい点数が取れたときは
- 毎日がんばって勉強したんだね!(努力)
- むずかしい問題にも挑戦できたね!(挑戦)
- いろんなやり方で問題に取り組めたね!(工夫したこと)
といった声かけを心掛けます。
普段から子どものことを観察していないとプロセスをほめることはむずかしいかもしれません。
日々子どもをよく観察しておく必要がありますね…!
2. もっと具体的にほめる
「おざなりほめ」には具体性が足りないため、もっと具体的にほめるようにします。
子どもが似顔絵を描いてくれたときも「上手に描けたね!」だけでは具体性に欠けてしまいます。
「よく顔を観察して、色使いもきれいに掛けているね!丁寧に描いてくれたんだね」のように
- 努力したこと
- 挑戦した姿勢
- やり方を工夫したこと
を中心に具体的に、どこがよかったのかを伝えるようにします。
大人も具体的なフィードバックをもらえた方がテンション上がりますよね…!
3. もっと質問する
ほめるだけでなく、子どもにどんどん質問します。
大切なのは
- 子どもがどう感じたか
- 子どもがどう思ったか
ということです。
親がどう思ったか(「すごい!上手!」など)はあまり重要ではありません。
会話のキャッチボールができるような質問で
- どこがいちばん大変だった?
- たのしかったところはどこ?
- どうしてそう思ったの?
などの自由回答形式の質問がおすすめです。
ほめるだけでなく、子どもに質問することも大切です。
自分でできる子に育つ「叱り方」

「叱り方」のポイントは、以下の4つです。
- 「ダメ!」「違う!」をできるだけ使わない
- 結果ではなく努力やプロセスに目を向ける
- 好ましくない行動の理由を説明する
- 親の気持ちを正直に伝える
叱り方の4つのポイント
1. 「ダメ!」「違う!」をできるだけ使わない
ダメ!違う!を言う前に
- 子どもが何をしたかったのかを理解する
- ありのままの子どもを受け入れる
ことが大切です。
子どもがスーパーなどで走り回ってしまったときに「ダメダメ!」と否定する前に「走りたかっただけなんだ!」と子どもの気持ちを理解します。
その次に「ここで走ると人にぶつかって危ないから、買い物が終わったら公園に行こうね」などと声をかけることを心掛けます。
2. 結果ではなく努力やプロセスに目を向ける
叱るときも「努力」や「プロセス」に目を向ける必要があります。
特に「人中心の叱り方」である、
- 子どもの性格・能力
- 外見の欠点
- 短所
などを責める叱り方をしてはいけません。性格や能力はすぐに変えることはできないため、子どもはどうしたらいいのか分からなくなってしまいます。
プロセスに目を向ける方法は、以下の通りです。
■ テストで悪い点数を取ってしまったとき
・「頭悪い!集中力が足りない!」(能力・短所)
・「次のテストでもっといい点を取るためにはどうしたらいいかな?」(プロセス)
叱るときも「努力」や「プロセス」に目を向けてあげるようにしましょう。
ここでも「質問」のスキルが大切になりそうです!
3. 好ましくない行動の理由を説明する
叱るうえで、子どもがとった好ましくない行動の説明をしっかり説明する必要があります。
なぜなら、説明しないと自分の行動と結果の因果関係を子どもは理解できないからです。
たとえば
■ 結果:
おともだちが泣いた(おともだちは悲しかった)
■ 原因:
おともだちを叩いた
のような結果と原因の「因果関係」もしっかり説明しないと子どもには理解できません。
「ダメでしょ!」の一言で済ませるのではなく、好ましくない行動の理由をしっかり説明することが大切です。
4. 親の気持ちを正直に伝える
親自身が気持ちを正直に伝えるようにします。
- 相手を批判したり、否定したりせず
- 自分自身がどう感じているか
- また、その理由は何か
を中心に伝えます。
たとえば、おともだちにオモチャを貸してあげられないとき「独り占めはダメでしょ、貸してあげなさい!いけない子ね!」と否定してはいけません。
「もっと遊びたかったんだね。ただここはみんなの場所だから、みんなで楽しく過ごせたらママ(パパ)はうれしいんだけどな」というように伝えます。
相手を批判・否定するのではなく、自分(親)の気持ちを正直に伝えるようにしましょう。
わたし自身が中心のコミュニケーション方法を「わたしメッセージ」というそうです!
ご褒美と罰がどちらもダメな理由
子育てにおいて「ご褒美」も「罰」もいい影響を与えません。
なぜなら、
- どちらも与え続けないといけなくなる
- 子どもが自己中心的な考えになる
などの理由があるからです。
ご褒美も罰も、一時的には子どもをコントロールできても、根本的に変えることはできません。
■ ご褒美がダメな理由
・ご褒美の依存が強くなる
・次はどうやったらほめられるか?ということに意識が向くようになる
■ 罰がダメな理由
・効果がなくなれば、別の罰を与えないといけなくなる
・罰を与えるほど、子どもは反発するようになる
ご褒美も罰もいい影響は与えないため、本書で紹介されている「ほめ方」と「叱り方」をしっかり押さえておきましょう!
まとめ
この記事では
- 自分でできる子に育つ「ほめ方」
- 自分でできる子に育つ「叱り方」
- ご褒美と罰がどちらもダメな理由
などをお伝えしてきました。
多くの人がほめるときに「すごいね!天才だね!」と言ったり、叱るときに「ダメでしょ!」と言ってしまうと思います。
しかし、ちょっとの心掛けで子どもの受け取り方が180°変わることを本書から学べました。
この本には、他にも「ほめ方」「叱り方」のケーススタディが満載です!詳しくはぜひ「自分でできる子に育つ ほめ方 叱り方|島村華子」をお読みください!
Kindle Unlimitedなら無料体験中に読めるのでおすすめです!
\ 無料で30日間お試し可能!/